教授あいさつ
沿革
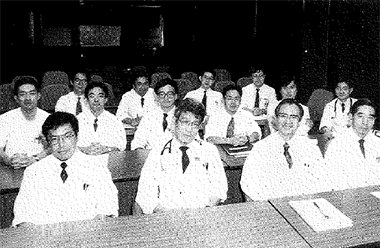
1990年11月1日、老化全般にわたる診療・教育を行い、豊かな高齢化社会づくりに寄与することを目的として、京都府立医科大学附属脳・血管系老化研究センター(老化研)が設置されました。当センターは、臨床1部門、社会医学1部門、基礎3部門(病態病理・細胞生物・分子遺伝)からなり、この臨床部門として神経内科学教室は設置されました。秋田県立脳血管研究センター病院長であった中島健二先生が初代教授に就任されました。1991年4月に教授以下、旧第1内科、第2内科、第3内科の神経部門から集結した講師・助手5名の6人体制でスタートし、翌年には3名の助手が加わりました。開設当初は、認知症に対する有効な薬剤がまだ存在しない時代でしたが、すでに多数の認知症患者さんが来院されており、教室では将来の高齢化社会を見据えて、積極的に認知症診療に取り組んできました。また大学病院として脳卒中診療に力を入れている教室も少ない時代でしたが、積極的に救急の患者さんを受け入れ、その中で多くの若い医局員が脳卒中診療に興味をもち、脳卒中の専門医として育ってきました。

2002年10月1日より、二代目教授として鹿児島大学第3内科(現神経内科・老年病学)講師であった中川正法先生が就任され、従来の脳卒中、認知症に対する診療に加えて、遺伝性神経疾患やHTLV-1 associated myelopathy (HAM)など神経難病への対応が強化され、専門的な診断・治療体制が大きく整備されました。また本学附属病院リハビリテーション部との連携により、脳卒中の急性期リハビリテーションに加え、パーキンソン病やHAM患者に対する専門的リハビリテーションにも力を注ぐようになり、チーム医療のさらなる充実が図られました。
2013年4月1日、中川正法教授が本学附属北部医療センター(旧京都府立与謝の海病院)の病院長に就任され、同年8月1日付で水野敏樹教授が第3代教授として本教室を継承しました。水野教授のもと、脳卒中、神経難病、認知症に加え、てんかん、頭痛、神経免疫疾患など多岐にわたる専門外来が整備され、診療の幅が大きく広がりました。さらに、研究活動も活発化し、脳神経内科のいろいろな領域で学位を取得する若手医師が続々と育ち、国内外への留学も積極的に行われています。2022年には大学附属病院にもStroke Care Unit(SCU)が開設され、2024年には京都府の救命救急センターの指定を受け、救急患者がさらに増加し、急性期脳卒中医療にも一層注力しています。
そして2024年12月より、尾原知行が第4代教授として教室を引き継ぎ、新たな体制のもとで診療・教育・研究を行っています。2025年7月現在、大学講座内でのスタッフ医師は12名、脳神経内科同門会の会員数は150名を超え、京滋地域を中心に15の基幹病院へ常勤医師を派遣し、地域医療への貢献にも力を注いでいます。

2024年12月1日付で、京都府立医科大学脳神経内科第4代教授を拝命いたしました。京都府立医科大学脳神経内科は1990年の設立以来、脳血管系老化研究センターの一部門として、「脳卒中」と「神経疾患」を診療と研究の両輪に掲げ、成果を積み重ねてまいりました。歴代の先生方が築かれた確かな伝統を受け継ぎつつ、これからの時代にふさわしい教室の発展と、次世代を担う医師・研究者の育成に全力を尽くす所存です。
脳神経内科が対象とする疾患は、脳卒中、認知症、パーキンソン病、頭痛、てんかんといったcommon diseaseから、多発性硬化症や視神経脊髄炎、重症筋無力症といった神経免疫疾患、さらには神経変性疾患や遺伝性疾患など希少疾患に至るまで、多岐にわたります。近年各領域での治療の進歩は目覚ましく、分子標的薬や核酸医薬品の登場によって、これまで治療が難しかった疾患にも新たな光が差し込んでいます。こうした医学の進歩をいち早く診療に取り入れ、若い患者さんから高齢の患者さんまで、京都府の脳神経内科医療を支える責務を果たしてまいります。
研究面において、私たちはこれまで臨床研究から基礎研究まで幅広い分野に取り組んでまいりました。脳卒中では臨床データを活用した治療予後の解析や、画像診断を用いた病態の解明に注力し、治療戦略の向上に寄与してきました。認知症やパーキンソン病の分野では、バイオマーカーの探索を通じて早期診断と病態理解を進め、より効果的な介入法の確立を目指しています。その他にも神経筋疾患の電気生理・神経超音波による病態解析、遺伝性神経疾患の病態解明、頭痛、てんかん、神経免疫疾患の病態解析などをテーマに研究を行っています。「ベンチからベッドサイドへ」の姿勢をモットーに臨床と基礎を結ぶ研究を推進し、脳神経内科領域のさらなる発展に寄与したいと考えています。
患者さんのため、未来の医療のために一丸となって医局員一同精進してまいりますので、どうか今後ともご指導ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。